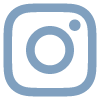2025年3月議会一般質問⑤【地域防災計画の見直し①】
5:地域防災計画の見直し
Q:帰宅困難者対策のマニュアル策定
(黒口)
5つ目の視点は、本市の防災減災への取り組みです。市長は提案理由説明で能登半島地震という大規模災害の教訓を生かし、災害対応の実効性を高めていかねばなりませんと述べられました。防衛省予算案に盛り込まれた事業については、どれも必要なものばかりと受け止めておりますが、重要なのはまさに実効性ある取り組みかどうかではないでしょうか。この観点からお尋ねします。
一つ目は。帰宅困難者対策です。 誘導体制マニュアルを作成して。いくにあたり、どのようなデータや知見に基づいて作成するのか確認したいと考えています。私はこのテーマに関し、仙台市を視察しました。 仙台市では、東日本大震災で生じた帰宅困難者の問題について、実際帰宅困難者がどの程度生じたのかを推計しているだけでなく、発災後、帰宅困難に陥った人たちを避難誘導した結果。近隣の避難所や施設ではどんな問題が起きたのか、また、避難誘導されていない人たちはどのような行動をとったのかと、その状況を調べ、写真を収集し、どんな支援が必要だったのかを考える根拠となっていました。
本市のマニュアル作成にあたっては、帰宅困難者の人数規模については、今後示される県の新たな震災想定に基づくと理解しています。 一方帰宅困難者の行動については、実際どんな動きだったのかは、能登半島地震発生直後の状況を調べることで、推測でなく実際の結果を知ることができるものと考えます。 本市として帰宅困難者対策のマニュアルができた後は、民間事業者と訓練をされる方針が示されています。
実効性の高い訓練となるためにもこの観点は重要と捉えており、能登半島地震発災の昨年の元日から2日にかけて本市で把握している金沢駅周辺での状況は実際どうだったのか、その調査から見えてきた対応の課題は何なのか、危機管理監にお尋ねをいたします。
■答弁:危機管理監
最初に帰宅困難者対策についてでございますが、能登半島地震発生時、金沢駅周辺に多くの方が滞留し、一時的に近隣の商業施設や宿泊施設等に避難したほか。避難所である公共施設にも多くの帰宅困難者が避難いたしました。
このことから、金沢駅周辺における避難場所の確保と避難者の誘導が課題であると捉えており、明年度、観光客などの帰宅困難者に対する迅速な対応を図るため、交通事業者や商業施設と連携した誘導体制マニュアルを作成するとともに、合同実地訓練を行うこととしております。